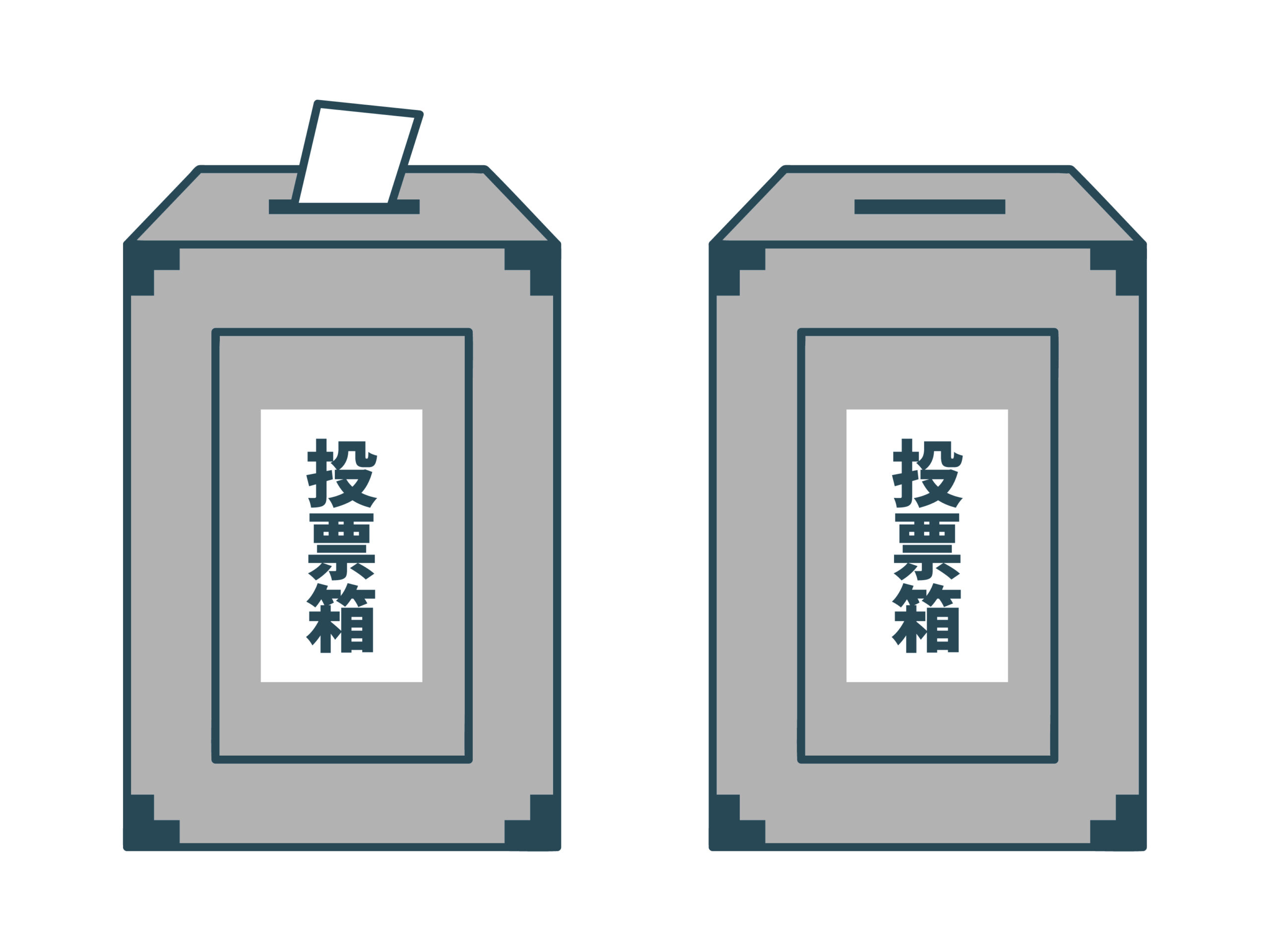現代の日本は、個人の自由が十分に保障されていて、かつ、広く人々が政治に参加できる民主主義国とされています。ところが近年では選挙を経ていない人たちの意向で政治的な決定がなされるのが目立ってきています。また、政治家が選挙時に公約などで言っていたことを実施しなかったり、言っていなかったことを実施したり、さらにその説明も不十分であることが目立ち、民主主義の根幹が揺らいでいます。揺らいでいる件の詳細は別の機会としますが、近代以降の民主主義における選挙というのは、世界では18世紀、日本では19世紀に実施されるようになったもので世界、日本の歴史からみれば、まだ歴史の浅いもので、まだまだ不完全なのも仕方ないのかもしれません。

民主主義国家で、議員などを決めようとすれば、選挙での多数決以外に方法はないだろうと多くの人が考え、様々な投票方法が考案されてきましたが、それぞれ問題点を抱えているのです。
今回はその問題点について考えてみました。
①単純多数決方式
地方自治体の首長選挙などで用いられる単純明快な方法です。問題となるのは3人の候補者がいて最多得票で勝利した人の得票率が50%未満の場合です。この場合、2位と3位の候補者の得票率の合計は、50%を超えていることになるので、3位だった候補者が立候補していなかったとしたら、その候補者の得票分は、1位か2位の候補者に渡ることになり、もしかしたら、2位の候補者が勝利していたかもしれないのです。実は本当に高い支持を得られている候補者が当選できていないということが起こり得るという問題点があります。
②決選投票方式
フランス、フィンランド、コロンビア、チリなどの大統領選挙、日本の国会での衆参両院での首班指名、オリンピックの開催地の決定などに用いられています。3者以上の候補から1番だと思う者を選び、単純多数決方式の欠点を補うため、1位が過半数に達しない場合、上位2者で決選投票を行うというものです。
最終的に過半数の支持を得た候補者が勝利するため有権者の納得感が高いというメリットがある一方、投票が2回に渡ることがあり、時間や手間、お金がかかるという問題点や、一回目の投票で1位の候補者がぬか喜びすることなったり、よからぬ「工作」を疑われやすいという問題点を抱えています。覚えている方もおられるかもしれませんが、1984年、2回目の札幌オリンピックを誘致した際、1回目の投票で1位となった札幌が2回目の投票でサラエボに負けるということが起こりました。
➂ボルダ方式
日本のプロ野球での年間最優秀選手(MVP)を決める記者の投票、サッカーの国際サッカー連盟(FIFA)の年間最優秀選手賞を決める各国代表チームの監督と主将の投票などでは、この方法で行われています。
有権者が、複数の候補者に順位をつけ、第1位にA候補、第2位にB候補、第3位にC候補などと投票します。順位ごとに第1位は3点、第2位は2点、第3位は1点という感じで点数を決めておき、開票では、候補者ごとに順位に応じた得点を合計、最終的に、最多得点を獲得した候補者が勝利するというものです。この方式は第1位だけではなく、第2位や第3位を含めた幅広い支持を反映できるメリットがありますが、投票や開票、集計がとても複雑になるという問題点があります。
また、投票であまり1位とされなかった人が勝利者となり得るという問題もあります。別の言い方をすればアクの少ない万人受けしやすい人に有利な方式とも言えますし、成熟して安定した集団内での投票に向いている方法だとも言えるでしょう。
④方式によって当選者が異なるケース
社会科学では有名なことだそうですが「3人以上の候補者がいる場合に、多数決による選挙制度が必ずしもうまく機能しない事例」として、このようなケースが想定されています。

9人の投票者が、A、B、Cの3人の候補者に投票して、1人の勝利者を決めるとして、各投票者は、下記のように候補者に対して順位付けをしているとします。

・単純多数決方式での勝利者はA
それぞれ第1位の候補者に投票することになるので、候補者Aが4票、Bが3票、Cが2票を獲得します。最多得はAです。
・決選投票方式での勝利者はB
1回目はどの候補者も過半数に達しません。上位2名の候補者による決選投票となり、1回目の投票で得票の多かった候補者AとBの2名での決選投票が行われることになります。決選投票では、1回目にCに投票していた投票者8と9が、第2位の候補としてBに投票します。この結果、候補者Aが4票、Bが5票となり、Bが過半数獲得です。
・ボルダ方式での勝利者はC
ボルダ方式では候補者ごとに点数の足し算をします。第1位を3点、第2位を2点、第3位を1点として点数の計算をしてみましょう。

候補者Cが19点で最多得点となります。
方式によって当選者が異なってしまいました。
⑤どの方式が良いのか?
支持が過半数に満たない人が勝つ可能性があり、投票者の意思が十分に反映されない単純多数決方式、時間と手間とお金がかかる上にぬか喜びや工作の疑いを持たれる決選投票方式、仕組みが複雑で投票も開票もたいへんで、さらに強い支持が少ない人が勝利しやすいボルダ方式はどれも一長一短です。時と場合によって使い分けるしかないような気もします。
その場合、3つの多数決の方法のうち、どの方法をとるかを決めなくてはならなくなるわけですが、多数決の方法についての話し合いがうまくまとまらなければ、どの方法をとるかを多数決で決める必要が出てきます。多数決の方法を決めるための多数決は、どの方式にすべきか……。と、話は迷路の中に入ってしまいます。
⑥民主主義の現状と展望
民主的な選挙は世界人口の半分が参加できるまで増加していたのですが、現在では減少傾向にあり、30%ほどにまで低下してきています。
そうなってしまった背景には、決定に時間がかかる民主主義よりも優れた指導者による独裁政治の方が優れているという、古代ギリシャ時代から言われている考え方が再び広まってしまったこと、公正な選挙ではない、いわゆる不正選挙の横行が大きいようです。
本当に優れた指導者が独裁政治を行うという「哲人政治」が実現すればよいのですが、ひとたび独裁者や少数のエリートが自分のための支配を始めると、これは政治の在り方として最悪であることは歴史が証明しています。近年言われるようになった「グローバリズム」は、言い換えると「世界政府もどきによる独裁」ですから、これは避けなければなりません。
民主主義は論理的にあり得る政治形態としては選挙制度だけでも根本的な問題点を抱えており「最善」と言えませんが、実在し得る政治形態の中では「もっともまし」だと言えます。
民主主義を維持するためにも、今回考えたような選挙システムの根本的な不完全さも基礎知識として知っておいた方が良いのではないかと思います。根本的な問題なので、さらに取り繕おうとして複雑化した現在の国会議員の選挙などでも解決せず、結果を見ればさらに問題が多様化、複雑化、深刻化しているように見えますので。